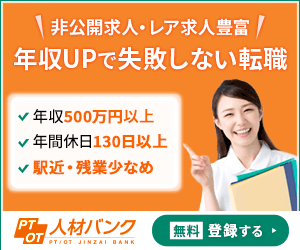リハビリ効果を上げる!5W1Hで適切な目標設定

リハビリの目標を患者者と共有できていますか?
目標を決めず、患者様が苦手な課題だけに着目していませんか?
目標がない場合、近づいていくゴールがなく、毎日苦手な課題を行うだけになりかねません。
最も苦手なことは長期的に達成できるように、段階付けて考える必要があります。
そのためには、整合性のある短期目標と長期目標を設定しなければなりません。
この記事では、目標設定の重要性や5W1Hを使った設定方法についてまとめてみます。
目標設定の重要性
適切な目標設定
- 生活や身体の変化を実感しやすい
- 状態に応じて実施するので対象者の負担が少ない
- 成功体験により意欲が上がる
- 改善している実感により希望が持てる
不適切な目標設定
- 同じ内容のリハビリを繰り返し変化に乏しい
- 苦手なことが中心になり対象者の負担が大きい
- 上手くいかないことが多く意欲が下がる
- 改善している実感が乏しく不安になる
目標設定が曖昧な場合、具体的な道筋がわからず、実施していることが本当に適しているかの判断も難しいように思います。
目標設定をしても「思うようにいかない」「意味がない」と感じるようになると、目標設定を行わない内容の薄いリハビリになってしまいます。
不適切な目標になる原因
- 非現実的な高い目標を設定する→回復がイメージできない
- 筋力や麻痺の回復段階を考慮していない→機能低下が目立つ苦手な課題から介入するのでリハビリが進みにくい
- セラピストが実施したい内容を優先している→問題点が不明確なまま方法だけを繰り返す
長期目標の設定
長期目標は疾患特性、年齢、筋力や麻痺の回復などを考慮しての予後予測になるので、現実的に設定ができるようになるにはある程度の経験が必要になります。
但し長期目標を設定する作業を怠ると、何年経っても予後予測ができないように思います。
不適切な長期目標になる原因
- 目標は高く設定する方がよいと思っている
- 対象者の訴えを具体的なイメージなく長期目標にする
- 疾患特性や年齢が考慮されていない
- 現状把握が不十分
- 身体機能とADL・IADLのつながりが理解できていない
麻痺や高次脳機能が劇的に回復したり、進行性の疾患が回復したりするのは非現実的です。
長期目標を設定するときは、現在のアプローチにより達成がイメージできる活動に設定します。
短期目標の設定
短期目標は達成することで長期目標に向かっていくように整合性を考えて設定します。
不適切な短期目標になる原因
- すぐに達成できない高い目標になっている
- 長期目標との整合性を考えていない
- 疾患特性や年齢が考慮されていない
- 現状把握が不十分
- 身体機能とADL・IADLのつながりが理解できていない
短期目標は、早期に達成できるように考えないとリハビリが進まなくなり、患者様の意欲も低下します。
短期目標を設定するときはすぐに100%達成できるイメージが持てる活動が好ましいと思います。
5W1Hを使った目標設定
5W1Hとは
5W1Hは意図を完結にまとめるための基本のフレームワークになります。
これを活用することで目標設定を明確にすることができます。
5W1H
- When :いつ(期限)
- Where:どこで(場所)
- Who :だれが(関係する人物)
- What :何を(課題、問題)
- Why :なぜ(理由)
- How :どのようにして(評価・治療方法、環境設定)
更に筋力やブルンストロームステージなど長期目標まで継続して測定する数値を決めておくことで、短期目標と長期目標が整合性のあるものになります。
目標設定の具体例
症例:A様の全体像
70歳代の女性で転倒により左大腿骨頸部骨折を受傷。人工骨頭置換術を施行し、術後1ヶ月で現在は歩行器歩行で病棟内自立。独居の方で受傷前は自宅から200ⅿのスーパーへ独歩で買い物へ行っていた。
①長期目標
- When :2ヶ月
- Where:院内、病院の敷地内
- Who :対象者
- What :患側下肢で片脚立位10秒可能なバランス能力の獲得により屋内外を独歩で200ⅿ程度安定して歩行ができる
- Why :退院後、自宅から200ⅿ離れたスーパーへ買い物に行くため
- How :体幹筋・患側の股関節周囲筋の筋力強化により、片脚立位を可能にする
〇2ヶ月後には、患側下肢の支持性改善により、屋外200ⅿ程度を安全に独歩可能な歩行耐久性、バランス能力を獲得し、自宅で自立した生活が送れるようになる。
②短期目標
- When :1日
- Where:病室の洗面所
- Who :対象者
- What :両側下肢へ均等に荷重しての立位保持が10分程度可能となることで歯磨き、洗顔動作を改善する
- Why :日常生活において患側下肢で荷重する機会を増やすため
- How :体幹筋・患側の股関節周囲筋MMT、FRTを指標にアプローチを開始する
〇患側下肢の支持性を向上し、1日で均等な荷重での立位保持が10分程度可能となる。よって病室では歯磨き、洗顔が歩行器や台にすがることなく実施可能となる。

まとめ
目標設定についてまとめてみました。
- 目標設定の重要性
- 不適切な目標になる原因
- 5W1Hを使った目標設定
目標はあくまでも予定なので、再評価と検証を繰り返しながらリハビリを進めていきます。
達成までの期間はセラピストの技量によっても変わるので、自分の技量を知り、自分で期限を決めることが必要に思います。