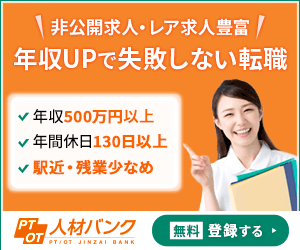リハビリを効率的に進める段階付けの考え方

「リハビリが思うように進まない」
「短期目標が達成できない」
このように悩むことはありませんか?
リハビリを効率的に進めるには、短期目標と長期目標との整合性のある段階付けが必要です。
段階付けを設定しない場合、その場しのぎの方法になりやすく長期的な目標に向かいません。
今回は私の段階付けの考え方をお伝えしたいと思います。
段階付けについて
段階付けとは
リハビリにおける段階付けとは、実施する難易度を状態や回復に応じて変化させていくことです。
目標を効率的に達成するためには、身体機能の回復過程や動作の難易度を理解し、順序立てれる必要があります。
できるだけ細かく段階付けることで、ゆるやかに階段を登るようにリハビリが進みます。
段階付けを考える際は、自分の感覚だけではなく医学的根拠に基づいて考える必要があります。
不適切な段階付け
①生活の順序を考慮していない
- 家の活動が不十分な状態で屋外歩行の練習
- 家での活動が不十分な状態で職場での作業練習
②身体機能と動作の難易度が合っていない
- 立位姿勢が整わない状態での歩行練習
- 座位姿勢が整わない状態での立ち上がり練習
身体機能と動作の難易度が合っていない状態で運動を続けると、痛みやスパズムの原因になることがあります。
運動の負荷が強くなるわりには成功体験が得られないので、意欲低下やリハビリ拒否につながる恐れもあります。
段階付けを行う際の基礎知識
運動機能の回復は運動発達の原則を知っておくと考えやすいです。
運動発達の原則
- 姿勢コントロール:頭部→足部
- 手足の運動:中枢部→末梢(粗大運動→微細運動)
- 決まった順序で発達:定頸→寝返り→座位→這う→つかまり立ち→歩行
- 手の発達:尺側→橈側、掌側→背側
運動発達を基に身体機能面での段階付けの例を挙げてみます。
①大まかな段階付けの例
- 得意な運動→苦手な運動
- 姿勢→運動
- 両側性の運動→片側性の運動
- 体幹の筋力→四肢の筋力
- 両側立位→片側立位
- クローズドループ→オープンループ
②詳細な段階付けの例
- ROM90°→120°
- MMT3→5
- ブルンストロームステージ3→5
- ファンクショナルリーチテスト20→30㎝
段階付けを行う際の注意点
疾患の特性や痛みについて把握しておかないと機能改善が難しい部分へアプローチしてしまう可能性があります。
特に禁忌事項が守れていない場合、リハビリにより状態を悪化させる恐れもあります。
- 疾患特性の理解
- 痛みの分類
- 禁忌事項の把握
例:大腿骨頸部骨折(人工骨頭置換術)
疾患について理解することで、機能回復が難しい部分、起こりえる痛みや禁忌事項がある程度わかります。
①疾患特性の理解
人工骨頭置換術による影響
- 大腿筋膜張筋の切開
- 大殿筋の切開
- 深層外旋六筋の切離
②痛みの分類
- 骨折による痛み:股関節近位部の痛み(多くは1週間程度で軽減)
- スパズムによる痛み:股関節内転筋群の緊張
③禁忌事項
過度の股関節屈曲・内転・内旋
段階付けの考え方
段階付けを考える手順
①長期目標の設定
疾患特性、年齢、病前の生活などから数ヶ月後にどのような生活が可能かを検討する。
目標達成に必要な身体機能をピックアップする。
②短期目標の設定
長期目標でピックアップした身体機能が向上するように、現在の身体機能からポジティブな要素を活かして、すぐに獲得できそうな動作を決める。
③長期目標と短期目標の間を決める
これが段階付けになります。
ピックアップした身体機能の回復に合わせて獲得できる活動を段階的にある程度決めておく。
段階付けの具体例
症例A様
70歳代の女性で転倒により左大腿骨頸部骨折を受傷。人工骨頭置換術を施行し、術後1ヶ月で現在は歩行器歩行で病棟内自立。独居の方で受傷前は自宅から200ⅿのスーパーへ独歩で買い物へ行っていた。
長期目標
2ヶ月後には大殿筋、大腿筋膜張筋、梨状筋の筋力が改善し、患側下肢での片脚立位保持が10秒程度可能。屋外200ⅿ程度を安全に独歩可能な歩行耐久性、バランス能力の獲得により、退院後は自立した生活が送れる。
短期目標
患側下肢の支持性を向上し、1日で均等な荷重での立位保持が10分程度可能となる。よって病室では歯磨き、洗顔が歩行器や台にすがることなく実施可能となる。
短期目標から長期目標までの段階
現状から2ヶ月後の片脚立位10秒、屋外独歩につながるように身体機能と活動の回復段階を考えてみます。
①初回の短期目標
- 立位バランス:均等な荷重での立位
- ADL:立位での整容(歯磨き、洗顔)
②第2段階
- 立位バランス:立位で患側下肢への重心移動
- ADL:トイレでのズボンの上げ下げ動作
⑤第3段階
- 立位バランス:手摺ありで健側下肢を台に挙げて患側下肢で保持
- ADL:手摺りを使って浴槽を跨ぐ
⑥第4段階
- 立位バランス:手摺なしで健側下肢を台に挙げて患側下肢で保持
- ADL:手摺りを使って階段昇降
⑦長期目標達成
- 立位バランス:患側下肢で片脚立位10秒
- ADL:屋外での安定した歩行

まとめ
目標設定をしても思うように進まないことが多いですが、目標設定をすることでセラピストは経験が得られ、対象者は回復している実感が持てます。
仮説検証を繰り返すことで、だんだんとイメージ通りにリハビリが進めて行けるようになるかと思います。